
書き出してみたら意外と面白い特徴があったKenko CLAMP POD PRO100で内容が埋まってしまったんで、残りのVelbon3兄弟のご紹介~
展開しきった時の外観なんかは前日のBLOGに貼られてるとかいう散らかりっぷりだけどそこがまた良い……はず。
(さらにGeo Carmagne E645L搭載雲台“PHD-61Q”と、ULTRA LUXi L(F)搭載雲台“PHD-41Q”についてはこの後の記事<LINK>に続く!)
●Velbon ULTRA LUXi miniの紹介●
この三脚は手持ちのVelbon三脚群の中では一番のちみっこ。
スペックもかわいらしい。(かわいいとか思うようになったら終わりだな……うん)
でもおねだんはなかなか小憎らしい!
・段数 6段
・開脚段数 3段
・縮長 215mm
・全高 591mm
・全高EV込み 678mm
・最低高 161mm
・雲台 QHD-61(クイックシュー無し)
・重量 850g
・最大積載量 2kg
・おねだん \19,740

展開サイズが小さいだけに比較的設置場所を選ばないのが良い。
 かと言ってこの例みたいに高所で設置するには何より勇気が必要だ!
かと言ってこの例みたいに高所で設置するには何より勇気が必要だ!
この時は前後左右に力を加え、まず落ちない……はず!
っていう事を確認しての撮影だった( ´-`;

ただ、小さいけれどガタツキは殆ど感じられず、雲台も大きい為安定感は抜群で、転落防止に足1本に軽く手を添えるだけで夜景もバッチリ!
他社製の三脚を使った事が無いのでどうかわからないけど、Velbonの三脚は足の角度を3段階に調整することが出来る。

高さを求める場合は標準(1段目)の角度で。
安定感、最低高を求める場合は3段目の角度で。
用途によってはその中間の2段目を使うと。
三脚自体の重量は約850gでCLAMP POD PRO100より重い。
しかし形状による先入観というか手が納得する形状のせいか重量バランスのせいかわからないけどCLAMP POD PRO100より軽く感じる。
まぁ、CLAMP POD PRO100の方が細身だからに違いない!
アスファルトの上、テーブルの上など地面が安定している場所で使う場合、角度3段目の状態でエレベータを外すと雲台上面まで約16cmという超ローポジションを取ることが出来、高い安定感がある為かなり重いレンズを使っていても安定する。
また、段数が6段ある足を全部のばした上に、エレベータも最大まで上げることで、約70cmの高さまで上げることが出来、あらゆる環境下(岩場など)での撮影の補助はもちろん、居酒屋なんかでの集合写真や旅行先での記念撮影に威力を発揮しそう。
●お次はVelbon ULTRA LUXi F(ULTRA LUXi L)の紹介●
この三脚はおいらが初めてまともに買った三脚で、11月22日の記事にある通り、Impressのこの記事を見て飛びついた一品。
この三脚を買わなければVelbonというメーカーに注目してないだろうし、Geo Carmagne E645L を手にする事も無かったかもしれない。
それほどまでに使える三脚なのであった!
まずはオフィシャルページのスペックを見てみる。
・段数 5段
・開脚段数 3段
・縮長 390mm
・全高 1360mm
・全高EV込み 1610mm
・最低高 190mm
・雲台 PHD-41Q(クイックシュー有り)
・重量 1320g
・最大積載量 2kg
・おねだん \22,260
奇抜な仕様は無く、“2009 SI-NA 三脚コレクション”の中ではもっとも標準的なのが特徴で、普通の用途以外での特徴は無い。
しかし一般的な三脚の機能はすばらしく、使い方によっては総重量3kgくらいの構成でも十分威力を発揮しそうなほど。
 梱包時約40cmで、EV込みの全高は約160cmにもなる。
梱包時約40cmで、EV込みの全高は約160cmにもなる。
この高さを実現する為段数が5段になっていて、その結果5段目の足は写真の通りかなり細くなる。
全ての足を伸ばしきりさらにエレベーターを上げきるとさすがに“しなる”けど、“ひねり”のゆがみは発生しにくい為、多少しなったところで2秒(ミラーアップ時のセルフタイマー)もあれば十分安定する。

 モードをミラーアップにし、「ミラーアップ」→「一拍おく」→「シャッターを切る」とすることでこんな写真が撮れた。
モードをミラーアップにし、「ミラーアップ」→「一拍おく」→「シャッターを切る」とすることでこんな写真が撮れた。
露光時間は7秒で、この間わりとしっかり止まってくれていた模様。


上の花火写真の下側、直線距離で3kmほどの街明かり部分を等倍で抜き出してみた。

ちなみに「一拍おく」を忘れるとミラーショックによりコウナル(×_×)
左は花火部分、右はイルミネーション部分。
まー、見るも無惨とはまさにこの事である。
ミラーショックでこの影響だから、風の影響はもろに受けてしまう。
もっともシャッタースピードを稼げる昼間の撮影であれば問題は無いかも。
条件によって使える場面が制限されてしまうのはどの三脚にも言えることだけど、このULTRA LUXi L(F)はかなりのシーンで“使う”事が出来るかなり有能な1本っすよ!
●最後は真打ちVelbon Geo Carmagne E645Lのご紹介!●
真打ちとか言ってるけれど実戦投入回数まだ1回のこの三脚。
それでもその1回がなかなか強烈なシーンだったんで、Geo Carmagne E645Lよかったぁ~と素直に思えた。
まずはオフィシャルのスペックを見てみる。
 ・段数 4段
・段数 4段
・開脚段数 3段
・縮長 674mm
・全高 1685mm
・全高EV込み 2010mm
・最低高 259mm
・雲台 PHD-61Q(クイックシュー有り)
・重量 2540g
・最大積載量 4kg
・おねだん \107,940
最大の特徴はやはり全高の高さ。
EVマックスで2m!
ベルボンの雲台セットシリーズでは上位の高さを誇る。
2mでカメラを設置すると、身長186cmのおいらはファインダーを覗くことが出来ない。(おーい)
仮にライブビューを搭載していてもピント合わせは不可能な高さ。
しかしこの高さが先日の高ボッチ再リベンジではものすごく役に立った。
現場では斜面に三脚を設置し、足2本は谷側へ、1本は足下に固定した。
で、谷側の足2本が50cm下に落ちてるから当然全高も下がるんだけど、EVを最大まで上げることで軽く膝を折る程度でファインダーを覗けるポジションを確保!
同時にセットしていたULTRA LUXi F は、「ありがとうございました!」とお客を見送るレストランのウエイターみたく、腰を90度に折るくらいの格好でやっとファインダーを覗ける高さに。
ULTRA LUXi F も平地でEVマックスだとぎりぎりファインダーを覗けるけどちょっと雲台を下に向けようものなら見れなくなるほどの高さを誇っていたはず。でも斜面という状況だとギリギリ高さを維持するのがやっとと言ったところかな。
そう考えると“大は小を兼ねる”し、1台目というなら兎も角、2台目であるなら迷わず背の高い三脚を狙った方が良いんじゃないかと思った。
因みに背の高さはさらに別メリットを与えられる。
高ボッチ再チャレンジもかなりの人が居たけど、人が多い場面では人の頭を越えることが出来る。
11月のチャレンジの時は「あと20cm高さを稼げれば!」と思ったことも……!
高さ以外の特徴は特になく、あとはカルマーニュシリーズ共通仕様が特徴といえば特徴かもしれない。

まず、本体に全部を覆うケースは付属せず、上の写真の通り石突の部分を覆うレグポシェットが付属する。
(全体を覆うケースも存在はするけど別売り)
 これがなかなかの役者っぷりだったりする。
これがなかなかの役者っぷりだったりする。
このポシェットにはバックルが2つ付いていて、1つにベルトを繋ぎ、片方を三脚本体のバックルに繋ぐことで“肩掛けポジション”を造ることが出来る。
ベルトの先端を両方ポシェットに繋げる場合は簡易ポシェットとなるそうだ。
まー、普通はその他バッグ類を持つことが多そうだからこの形態を取ることは殆ど無さそう。

 このポシェットには3方向にファスナーがついていて、どれかひとつを下げると締め付けがゆるみ、三脚本体からポシェットを“脱がす”ことが出来る。
このポシェットには3方向にファスナーがついていて、どれかひとつを下げると締め付けがゆるみ、三脚本体からポシェットを“脱がす”ことが出来る。
しかしそのファスナーの3方向全部を下げると写真のように広がる。
この状態で三脚の3本の脚に取り付けると“ストーンバッグ”に変身することになる。

しかし都合良く重しとなりそうなものが落ちてるとも限らないので、脚カバー以外の用途としては使わず、重しにはこれを使用した。
 エレベーターの終端にはUNC1/4仕様のネジがついていて、そこにフックを付けることが出来る。
エレベーターの終端にはUNC1/4仕様のネジがついていて、そこにフックを付けることが出来る。
高ボッチ再リベンジではこのフックにリュックをぶら下げ、振り子状態にならないように平地側の脚に固定ベルトで巻き付けて固定した。
Geo Carmagne E645L は全高が高い為、エレベーターを下げた状態であっても十分な高さがあるので手持ちの荷物をここにぶら下げて固定した方が展開時間の短縮にも繋がりそう。

で、なぜかそこだけ囲われた……、つまりレグポシェットの中にはコレが隠されていた。
 この三脚の石突は標準だと“ゴム”となっている。
この三脚の石突は標準だと“ゴム”となっている。
しかしその“ゴム”を回すとそのままスパイクが出てくる。
地面が雪・氷なんかの場合には当然こちらの方が効果がありそう。
今回の高ボッチではもちろんスパイク状態で利用! 安定感はばっちりだった。

因みに石突しか覆わないこのケースの使用感は……
悪く無い!
やはり展開が早いというのが大きいのと、梱包状態でもかなりの長さを誇るこの三脚。
中身がなんだか解らない長い物持ってるより、あからさまに三脚と解るこのケースはこのご時世に丁度いいのかも知れない。
あと、なんていうか格好良いし( ´-`)
ただ雲台の方も剥き出しなんで、どこかにぶつけて双方に傷つけるのはもちろん、人様にぶつけてケガさせないようにする事だけは最優先事項で気をつける必要がありそう。
さてこのGeo Carmagne E645L。
脚の太さといい、固定部分の頑丈さといい、剛性もばっちりで撮影時の安定感は文句の付け所が無い。
欠点という欠点が見あたらない……はずだった!
まぁ、これだけでの三脚でも欠点はある。
まずは大きさ! 収納状態でも70cm近い長さを誇り、エレベーターを使わない高さでも170cm高さまである為、極々普通の使い方をしているときには4段目を使用せず、エレベーターで調節しないとベストの高さに持って行く事が難しい。
とかなんとかいちゃもん付けても大きい三脚だから大きくて当たり前で、だからこそ選んでいるし、その辺は欠点とせずにそういう特徴と思って使用するのが正解。

となるとなんだろう?
最低高が約30cmという微妙なローポジション?
180度に近い大開脚となるので、展開径が1mオーバーとかなりの場所を取ってしまう。
しかしこれもそもそもの大きさが違い過ぎるので欠点とするにはちょっと可哀想だ。
 真の欠点はエレベータの固定方法!
真の欠点はエレベータの固定方法!
これには正直参ってしまった。
この三脚はレバーの上げ下げだけでエレベーターを固定出来る。
大きなメリットはやはり操作を迅速に行える所だろうか。
しかし高ボッチ撮影でこの操作最大の欠点に気づいてしまった!

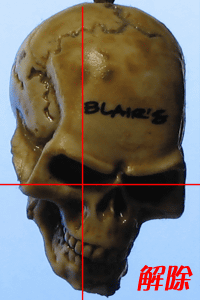 これはブレアーズのタバスコ40倍相当という激辛ソース (AA) についてきたキーホルダーを、Geo Carmagne E645Lに設置したPowershot S3 ISで撮影し、画像の中心部分を赤線で記し2枚切り換えて表示してるもの。
これはブレアーズのタバスコ40倍相当という激辛ソース (AA) についてきたキーホルダーを、Geo Carmagne E645Lに設置したPowershot S3 ISで撮影し、画像の中心部分を赤線で記し2枚切り換えて表示してるもの。
ロック時と解除時でこれだけ動いてしまっている。
600万画素のカメラでかなりトリミングしてるから、全体で見れば“誤差レベル”と出来るかもしれない。
しかしカメラは重量の軽いコンデジで、なおかつ焦点距離も50mmくらいでこれだけ差が出ているとも見れる。
事実DSLRで望遠レンズという重い組み合わせの時に重大な問題が発生した。
12/7の記事の後半に出てくる山の稜線をとらえた1枚。
山頂部を画面1/4下側に配置しロックした。すると山頂部が画面のほぼ真ん中に移動してしまったのだ。
エレベータ以外の方法を!
とも考えるべきなんだろうけど、縦位置にしたときに防寒カバーが邪魔して90度動かせない状況に陥った為、三脚を片側に偏って設置する形になっていた。
なのでパンハンドルを使うと斜めに移動してしまうという問題が発生していてこの時はエレベータで微調整を行っていたという訳。
いやいや、それくらいの誤差三脚では当たり前!
なのかどうかしらないけど、実はエレベーター固定方式がネジ締めタイプのULTRA LUXi F だとほとんど微動だにしない。
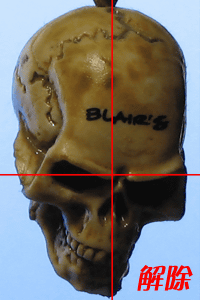 これは同じような高さに調整したULTRA LUXi F で撮影し、同じく中心線を赤で示した物。
これは同じような高さに調整したULTRA LUXi F で撮影し、同じく中心線を赤で示した物。
1ピクセルくらいしか動いていない。
これだけ頑丈な三脚なだけに、望遠かマクロで大活躍する……はずなんだけど、この結果はちょ~~っと残念。
でもまぁ、その他の部分では大いに満足しているので、この問題についても“癖”として意識していればそのうちこなれるに違い無い……ね!

以上!
2009 SI-NA 三脚コレクション おわり


コメント